お賽銭で五円玉がない時や使う意味は?縁起の良い金額が気になる!
Warning: Undefined array key 3 in /home/marumaru7202/marumaru7202.momorinn.xyz/public_html/wp-content/themes/luxech/functions.php on line 103
年始最初にすることと言えば、初詣ですよね。
初詣に欠かせないのが、参拝の時のお賽銭です。
お賽銭で使う小銭と言えば、五円玉ですよね。
ですが、参拝する時に五円玉がない時って結構ありますよね。
それに初詣に行くのが一つの神社だけなら良いのかもしれませんが、三社参りをする方も多いのではないでしょうか?
三社目の神社の頃になると、五円玉がない。もう小さい額の小銭がない。
など、500円玉しかなかった。や100円玉しかない。なんてことが多々ありませんか?
そもそも、もう小銭事態がない!!!
なんて経験をした方も多いのではないでしょうか?
そこで今回は、お賽銭で五円玉がない時や使う意味について。
また、お賽銭で縁起の良い金額はいくらなのかについても調査していきたいと思います。
お賽銭で五円玉がない時は?
お賽銭で五円玉がない時って結構ありますよね。
五円玉がない時に私が小銭を出す順番は、一円玉から使っています。
お賽銭に100円も使うなんてもったいない!と思ってしまうのは私だけでしょうか?
実際に五円玉がない時に使うと良い金額はいくらなのでしょうか?
五円玉以外で縁起が良いとされている金額に、二十円とあります。
二十円は、二重にご縁があり縁起が良いとされています。
また、20円に1円を足して21円にすることで、
恋人や夫婦の縁がきれないとも言われているそうです。
さらに縁起が良い金額が、五十円で五重に縁があるとされているそうです。
十円玉がお財布にたくさん入っていた方は、二十円入れるだけでも縁起がよくなりそうですね!
お賽銭で五円玉を使う意味は?
そもそもなぜ、お賽銭に五円玉を使うのでしょうか?
五円とご縁を掛けてるだけでしょー。
と思っている方も多いのではないでしょうか?
私もそう思っていました。
ですが、五円玉を使う本当の意味が気になったので調べて見たところ、
まず、「語呂合わせを使った金額を入れる」ことに意味があるそうです。
お賽銭で縁起の良い金額は?
五円玉には、一枚でも「ご縁がある」と言われています。
また、五円玉をたくさん用意することによってそれぞれに意味があります。
早速、お賽銭で演技の良い金額を見て行きたいと思います。
五円一枚で、「五円」と「ご縁」を掛けて「ご縁がありますように」
五円二枚で、「重ね重ねご縁がありますように」
五円三枚で、十五円と「十分ご縁がありますように」


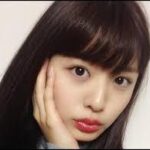

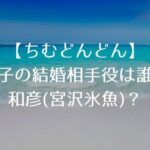

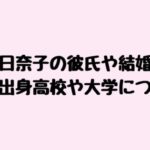
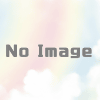


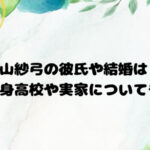
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません